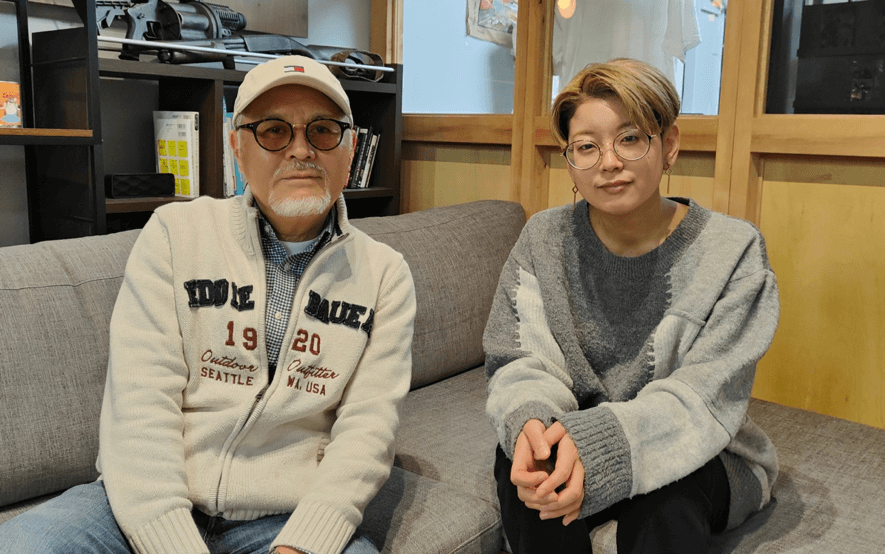シルヴェスター・スタローン製作総指揮のNetflixオリジナル作品や「情熱大陸」など日米で番組をプロデュース!最新作の短編映画『Perfect World』をロサンゼルスで製作・監督した深田祐輔さん世界で活躍するクリエイターに迫る!
ハリウッドの巨匠 ジョージ・ルーカス氏と同じ南カリフォルニア大学大学院を卒業し、今年9月にはオーストラリアのSciFi Film Festivalにて短編映画『Perfect World』上映を控える映画監督・深田祐輔さん。アメリカでの映画制作やNetflixでの映像プロデュースなど、日本よりも海外での映像制作活動の方が多いといいます。なぜ海外へ出ようと思ったのか、海外進出や海外での映画制作で大事なポイントは? 日本の枠を超えて活動する深田祐輔さんへインタビューを行いました。
■海外で始まった映画監督のキャリア

(写真提供:Weekly LALALA / 2017年8月25日号掲載)
−まず、日本での映画監督としてキャリアについてお聞かせください。
深田:2008年にある映画で現場に入らせてもらい、続けて現場のお仕事の声をかけていただいていたのですが、パリに行ってしまい参加できませんでした。日本ではその次の大きな仕事が、2019年の情熱大陸のプロデューサーだったので、自主制作を除けばお仕事として日本で映画に携わったのは2008年が最初で最後でした。
−海外での活動の方が多いんですね。
深田:プロジェクトの数で言えばそうなります。2012年に南カリフォルニア大学院に入学したのですが、そこで製作・監督したものが短編映画『Perfect World』です。アメリカではその他にシルベスター・スタローンさんがエグゼクティブ・プロデューサーを務めたNetflixオリジナル作品『アルティメット・ビーストマスター』でアメリカ版及び日本版のプロデューサーとして、またアニメ版の『ライオン・キング』などのプロデューサーであるドン・ハーン監督のドキュメンタリー作品『ギャンブルハウス』のサウンドデザインなどを担当させてもらいました。いずれも大学時代の友人や先生を通じてお仕事をいただいたのですが、「英語と日本語が喋れること、プロデュースができること、編集作業などのスキルがあること」という条件があり、そこにぴったりハマったという理由でしたね。
−パリやカリフォルニアへ進学などされていますが、最初から海外で映画を作りたい思っていたのでしょうか?
深田:高校の頃から海外には興味があったのですが、地元が京都太秦という映画の街ということもあったので、必ずしも海外で映画を作ろうとは思ってませんでした。ですが、京都フィルムメーカーズラボという若手育成ワークショップで出会ったプロデューサーの方に将来の方向性を相談させていただいた時、当時の日本映画の現状も踏まえ「海外に出るチャンスがあるなら行った方がいい」という言葉をかけられました。今から思えばやんわり就職を断られただけかもしれませんが(笑)、それがきっかけで海外に行って、勉強できることやって帰ってこようという決心がつきました。
■ アメリカだからできる映画作りを -短編映画『Perfect World』秘話-

南カリフォルニア大学での映画の撮影風景
−ロサンゼルスで制作された短編映画『Perfect World』ですが、この映画を作ろうと思った背景はありますか?
深田:もともと作ろうと思っていたアイデアが2つありました。ひとつが20世紀初頭のアジア人女優の物語でもうひとつが情報化社会をテーマにしたSF。いずれもマイノリティや社会の当たり前から外れた人を描きたい思いがあったのですが、「せっかくアメリカにいるなら、ここにいるからこそできる映画を作ろう」と思うようになりました。アメリカではアジア人はアジア人の物語を作るべき、というような強迫観念に似た雰囲気がどこかにあり、それに対する抵抗感があったのかもしれません。アメリカに来てから、日本では触れてこなかった最先端のテクノロジーにたくさん触れる機会があったので、同じ「マイノリティー」をテーマにするにしても、SF映画として表現しようと決め、完成したのが、『Perfect World』です。

(写真提供: EN Pacific Service Inc.)
−どのような思いで映画を制作されたのでしょうか?
深田:映画制作にあたって、まだ他の人がやってないこととか、自分がやったことがない撮影に挑戦したい、と思っていました。
ただカメラを回して撮るのではなくて、撮影の方法からもオリジナリティが出るようにしたいという思いがありました。どうしたら自分のコアの部分を映画に反映できるか考えた時に、見せ方で勝負しようと思い、ワールド・ビルディングという架空の世界観に統一感を持たせる手法や深度センサーを含む新しいカメラの使い方など、美術監督のローラチャハノウィッツさんやAFI(アメリカ映画協会大学院)で学ばれていた撮影監督の木津俊彦さんなどと一緒に、世界観と映像・音響の作り方を一から模索していきました。
ちょうど南カリフォルニア大学では映画制作の設備が整っていたので、そこでモーションキャプチャの技術を映画に取り入れて、データの世界を表現することにしました。そのおかげでオリジナルなビジュアルにはなったかなと思います。
−国内外での観客の反応の違いはありますか?
深田:日本人の役者さんが出ているいわゆる日本映画という訳ではないからだと思いますが、『Perfect World』については、国内外で反応の違いはそれほどないですね。エフェクトをたくさん使っているので、メディアアートとしてみられることも多いです。日本だとSFを見る文化が一部のSFファンに限られる傾向があるので、SFファン以外の方には情報社会の格差の物語として、SFファンの方には変わった映画を日本人の監督が頑張って作ったなと面白がられることが多いです(笑)。
映画では「全てがデータ化されて、データで人が判断するような近未来」を写しているのですが、制作当初から「近未来のドキュメンタリー」を作るような意識を持っていました。制作開始当初は近未来の話として作ったものも、データを元にしたスコアなど、今では当たり前になってきていることもたくさんあるので、その意味で観てくれる人にはより身近な世界として感じてもらえたら嬉しいですし、この映画をきっかけとしてみなさんと話してみたいことがたくさんあります。
■ 「プロデュースもできる監督」を意識

(写真提供:Weekly LALALA / 2017年8月25日号掲載)
−映画監督をする上で意識されていることはありますか?
僕自身、映画監督 兼 プロデューサーというのを意識しています。海外に出るまでは、監督といえば自分の世界を貫く「アーティスティックな人」をイメージしてたのですが、南カリフォルニア大学に行ってからは、人と人とのコミュニケーションをとる「プロデューサー」的な存在を意識するようにしました。日本では空気を読むことが尊重されますが、そこから少し踏み出してコミュニケーションが取れるようになったと思います。こう行ったスキルは海外でやるのには特に重要だと思っています。日本では監督とプロデューサーが分業する場合が多いですが、アメリカではこういう人は意外と多いですし、それがよりスタンダードになっていくと思います。
−深田監督のように、日本と海外の間に立っている監督は少ないと思います。積極的に海外に出てよかったと実感することはありますか?
自己プロデュース能力や、プレゼン能力は鍛えられましたね。『Perfect World』の現場でも、演技や編集に対して感性の部分をクルーに英語で納得してもらわなければなりませんでしたし、今では笑い話ですが『ビーストマスター』でグラフィックに使う日本語が中国語フォントで表示されていて、「ン」と「ソ」が見分けがつかないというのをアメリカ人のシニアプロデューサーに理解してもらうのに苦労したりと、「あたりまえ」が効かない現場で要求される柔軟性や強さみたいなものは身についたような気がします。
これは経験上ですが、海外の人は日本人のいち映画監督には基本的には興味がない。その前提から入ると、自分のことを売り込んだり、映画の撮影で意見を主張したり、時には交渉することって、文化とかバックグラウンドが違う人へ納得してもらうスキルになるのでものすごく大事だと思います。自分の考えを伝えたり、意見を通したりできることで、個人として認められていったと思います。これができることが、プロデュースができることではないかなと思っています。
ロサンゼルスでは、日本人がプロデュースをする場合、これまでは日本発のコンテンツを扱うか、現地の作品であればコーディネーター的な役割を担うプロデューサーが多かったかもしれませんが、これからは「自分の考えを納得してもらう」、「ビジョンを押し通せる」クリエイティブなプロデューサー/ディレクターがより求められると思いますし、僕もその一人として成長できればと思っています。
■ 「100ヶ国×100人」のファンを ー海外進出の魅力とは

(写真提供:Weekly LALALA / 2017年8月25日号掲載)
ー日本映画の海外進出についてお伺いしたいです。海外での上映会や国際映画祭への応募など、海外進出にあたり大変なことはなんですか?
自分の映画作品にあった映画祭(出口)をピンポイントで探すのが難しいですね。たとえば、過去にアジア系の映画祭なら入りやすいかな、と思って応募してみたのですが、全然入選しませんでした。よく考えたら『Perfect World』はアジアの要素がほとんど入ってないんです。映画内に日本人が登場するわけではなく、日本らしい要素があったわけでもなかったので、入選しにくかったんだなと、後から気づきました。
−映画祭にも相性があるんですね!
海外の映画祭にかかるには、映画の「ジャンル」「出演者」の場合もあれば、いろんな「入選」のポイントがある。どの属性をアピールポイントとして使うのか、それを考えるのが大変です。
だから、フィルミネーションのように登録するだけで海外のVOD社との関わりはこれから映画を作って生きていく上で鍵になると思っています。映画祭への出品料などの経済面はもちろん、自分の作品にマッチした相手を探す時間のコストが大幅に削減できる。ある意味、映画界の働き方改革ですね(笑)特にキャリアの浅い映画を志す人にとって、映画・映像を作って生きる可能性が広がると思います。
−そのようなお言葉をいただけるのはとっても嬉しいです(笑)
確か黒沢清監督が言ってた言葉なのですが「同じファンが1万人でも、日本人を1万人集めるのは大変。だけど、海外なら100ヶ国で100人のファンを作ることが可能になる。」海外に出るって発想であり、海外に映画を出す魅力はそこなのかなと思います。100ヶ国にアプローチしたり、各国の言語でアピールするなんて、それだけでコストがかかりますし、物理的に不可能ですが、これからテクノロジーの進化に伴って、そういう部分で可能性がどんどん広がっていくことを期待しています。
深田監督、ありがとうございました!
■作品情報
短編映画『Perfect World』

(C) 2018
【物語】
生まれてくる子供の能力(SPEC)を、事前にデータで判断できる」あらゆることがデータとして捉えられるようになった、近未来の2121年では、出産前に子供のSPECを測ることが義務付けられ、社会の役に立たない ”低SPEC” と判断された子供は、堕胎しなければならない。
そんな世界で「堕胎専門医」として務める医師DR_06。日々、低スペックの子供を堕胎する中、ある日病院にやってきたのは妊娠中の元恋人だった。
製作総指揮・監督:深田祐輔制作国:日本/アメリカ
Latest columns
- Interview